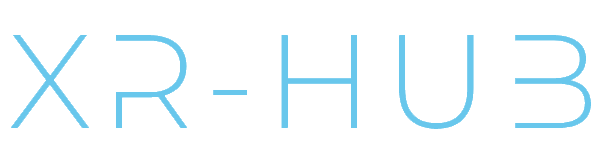【AR/MRコミュニティ】Spatial Computing Lab 2期生の作品をご紹介!
大学生のAR/MRクリエイターが集い、アイデアを形にするクリエイティブサークル「Spatial Computing Lab」。
本記事では、前回の第1期生に続き、第2期生が創作した作品について紹介していきます。
空間コンピューティング時代を見据えた、若手クリエイターの熱意ある作品の数々、是非ご覧ください!
S.C.Lの応募はこちらから
Spatial Computing Lab とは?

Spatial Computing Lab(以下S.C.L)は、「Draw the Spatial World -空間コンピューティングが浸透する未来を引き寄せる」をミッションとした大学生のためのAR/MRクリエイティブコミュニティです。
Spatial時代を手繰り寄せるべく、ARやMRといった先端知を自らで「創造」し、世界に「発信/還元」しています。
第2期生は2020年の9月からプロジェクトがスタートし、4ヶ月の創作期間を通して作品を表現してもらいました。
本プログラムでは、MRデバイス「Magic Leap 1」向けのアプリケーションの開発に挑戦しました。
PET OWNAR
作品紹介
Created by:Fal、長谷川
「PET OWNAR」は『ARグラスが普及した未来のペットを体験してもらいたい』という想いから制作された作品です。
作品はUnityで制作されており、操作にはコントローラとハンドジェスチャーを使用します。
体験は寝ているペットを起こすところからはじまり、猫じゃらしで可愛がったり、発射したボールをとってきてもらったり、ご飯を与えたりします。
その後、お腹いっぱいになり遊び疲れて寝てしまったペットを寝床に戻すところで終了です。
もしやるべきことが分からなくなっても各体験ごとにチュートリアルが準備されており、バンパーを押すことで直前のチュートリアルを表示できます。
ペットのデザインや動きの自然さなど、まるで本物のペットと遊んでいるような愛情を感じるハートフルな作品になっています。
将来、ARグラスが普及した未来ではこのようなペットの存在も1つの選択肢になってくるのかもしれませんね。
メンバーコメント(Fal・長谷川)
【作品についてのコメント】
メディアの進化によってデジタルとフィジカルは融和していくと言われますが、これはバーチャルなペット(たまごっちなど)とリアルなペットの境も同様であるという仮説を立てました。
現在、環境や身体、時間、金銭といった様々な問題でペットを飼えない人々の数は少なくありません。
私たちはARグラスによってこの問題を解決する新しいペットの選択肢を生み出すことができると考え、本コンテンツ『PET OWNAR(ペットオーナー)』を制作しました。
将来的には餌や服の購入システムなどを実装し、ビジネス面としても可能性のあるコンテンツを目指していきたいと考えています。
ぜひ本作品にご興味があれば遠慮なくご連絡ください。
【プログラムを経ての感想】
主にUnityでの実装とペットのキャラデザイン、モデル制作を担当しましたFalです。
私はS.C.Lでの活動が始まるまで個人での開発経験しかなかったため、今回の2人での開発はとても新鮮な体験でした。
お互いの持ち味を生かしながら制作を無事終えられたことが何よりも嬉しいです。
シーン全体の流れおよびチュートリアル部分の制作を担当した長谷川です。
私も複数人での開発は初めてでしたが各々の忙しい時期にフォローしあえたり詰まったところはすぐ話し合えたりしたのでうまく進められたのではないかと思います。
また隔週の定例会では様々な意見をもらうことができ自分たちでは考えつかなかった多くのアイデアをコンテンツに反映させることができました。
Project egg
作品紹介
Created by:保坂
Project eggはゲームと現実の境目を曖昧にすることをテーマに作られた、ARグラスを用いた没入型体験ゲームです。
「エッグ」という次世代バーチャル生命体が逃げ出してしまい、偶然居合わせた体験者がエッグたちを回収しにいくというストーリーになっています。
逃げ出した3体の生命体はそれぞれ特殊な能力を持っており、捕まえるには一工夫必要です。
そこで事前に渡された資料ファイルをヒントに様々なアイテムを駆使して進めていきます。
また、ゲームはハンドジェスチャーのみでプレイすることができ、捕獲ジェスチャーを行うことで逃げ出したペットを捕獲することができます。
ハンドジェスチャーのみでできるからこそ、自分が主人公となって今いる現実で物語の世界を体験できることが本作品の魅力です。
細部の作り込みも凄く、Spatial Computing時代の参考になる、非常に高いクオリティのゲームになっております。
メンバーコメント(保坂)
【作品についてのコメント】
「Project egg」は「物語と現実の境を曖昧にする」をコンセプトに開発した体験型ゲームです。
ゲームキットやストーリーによる情報的演出とARを用いた視覚的な演出により、物語を傍観するだけでなく体験者が当事者だと感じるような没入感を目指しました。
捕獲アクションやゲームキットの作りこみは特に力を入れました。
【プログラムを経ての感想】
S.C.Lのプログラムはとても楽しかったです。
自分の理想のコンテンツを今の自分の実力の中で何とか形にできたと思いますが、一方で現状の実力を把握でき、かつ様々な反省点が明確になったのも有意義でした。
またSCLメンバーから貴重な意見やフィードバックをもらうことで、作品をより良いものにできたのもこのプログラムの良い点だと思います。
BEAsTS
作品紹介
Created by:マチコー、はま、じぇい
「BEAsTS」は、共感覚をテーマとして音楽と溶け合うような体験を目指した作品です。
ハンドジェスチャーによって音楽を奏でるドラゴンたちを好きな場所に配置します。
Magic Leapのコントローラーを指揮棒として振り上げるとドラゴンたちが静まり返り、演奏の準備をします。
あなたがオーケストラの指揮者となり、指揮棒を振ってドラゴンたちの演奏をまとめましょう!
現実空間を歩き回り、ドラゴンたちの音色を聞こえ方の違いを楽しむことや、指揮棒を振るテンポを変えてみて、音楽に溶け込むような体験を楽しむことができます。
初めて遊ぶ人でも体験しやすいようにチュートリアルを準備しているところや、細部のエフェクトを拘って実装しているところなど開発チームの拘りが強く感じられます。
共感覚という未知の感覚を体験できるMR時代の素敵な作品です。
メンバーコメント(マチコー)
【作品について】
BEAsTSは「映像(視覚)や音楽(聴覚)がインタラクティブな体験を伴って交錯する」感覚・印象を『シナスタジア(共感覚)』と定義し、ARグラスを用いてエンターテインメントとして昇華させることを目標とした作品です。
EnhanceやGATARIの方にもフィードバックをいただき、特に空間演出に力を入れました。映像と音楽と身体が交錯するような体験を、どうぞお楽しみください。
【プログラムを経ての感想】
私はプロジェクトマネージャーだけでなくコミュニティリーダーも務めていたのですが、S.C.Lの皆さんの情報感度の高さには毎回驚かされていました。
最先端の技術領域に挑戦したいと考えている方、また私のように技術をコンテンツとして広く普及させたいと考えている方、両方が活躍できる点がS.C.Lの良いところだと思います。
AR/MRはいまだ未開拓の領域が多く残る、魅力ある分野です。今後も開発を続けていき、普及啓蒙を行ってまいります。
流れ星万華鏡AR
作品紹介
Created by:安黒
「流れ星万華鏡AR」は、万華鏡の空間で流れ星を放ち、キレイな模様を眺める作品です。
コントローラーで流れ星を放つ数や色を変更することができ、流れ星を放つ力や向きによって様々な模様の万華鏡を作ることができます。
体験者が自由に模様を作れるため、一番キレイな模様を探す体験が本作品の一番の魅力です。
Magic Leap上で色とりどりな流れ星を自分で描き、キレイな空間を創り出してみてください。
メンバーコメント(安黒)
【作品について】
あらかじめ用意されている3DCGを眺める体験よりも、自分自身で創意工夫してキレイな3DCGを作る体験ができた方が楽しいのではないかと思い、流れ星万華鏡ARの開発をしました。
実はこの作品は1ヵ月くらいの短期集中で制作した作品です。
短期集中ということでどのように実装すれば簡単に作れるのかを考えたため、比較的に短い期間の割には楽しめる作品を作れたのかなと思います!
【プログラムを経ての感想】
このアプリを開発する中で没になってしまった体験内容がありました。
具体的には華鏡の中心軸を自由に設定し、例えば横から万華鏡を覗き込む体験というものでした。
しかし、万華鏡を横から覗き込む体験をしたとしても、あまりキレイな模様にはならず、その機能によって操作が複雑になってしまうため、結果として不採用となりました。
こういった改善案をしてくださったのは、実はS.C.Lメンバーでして、客観的な視点からのアドバイスはとても参考になりました!
さいごに
以上がSpatial Computing Lab 第2期生の作品になります。
1期生に続き、Spatial Computing Labの学生の方々は成長意欲が強く、お互いに良い刺激を与えあい急激に成長していく姿がとても素敵でした。
また、コロナによってメンバーで集まりにくく開発が難しい状況でも自分達なりに工夫をして開発をやり切ったメンバー達がとても頼もしかったです。
引き続き次世代を担うXRクリエイターの登竜門となるよう努力してまいりますので、応援のほどよろしくお願いします!
Spatial Computing LabやAR/MRに興味のある学生は、ぜひご連絡お待ちしております。
S.C.Lの次期応募はこちらから
S.C.L第1期生の作品は以下の記事にまとめてあります。
参考記事)【大学 ARサークル】Spatial Computing Labの第1期生の作品に迫る!
SCLの所長・副所長の想いや今後の展望については以下の記事をご覧ください。
参考記事)【Spatial Computing Lab創設者対談】大学生AR/MRコミュニティ創設に込められた想いと展望
また、MagicLeapの開発に興味がある方は以下の記事もご参考ください。
参考記事)【MagicLeap入門】Unityのセットアップ手順を1から解説!

この記事はいかがでしたか?
もし「参考になった」「面白かった」という場合は、応援シェアお願いします!